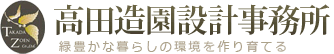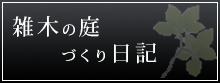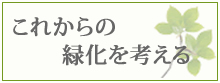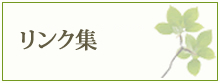2015年11月23日 月曜日
種にかえる季節
秋の賑やかさも落ち着き、道に溜まった落ち葉から早くも暮れの足音が感じられます
冬は寂しさを感じますが、生き物全てが次の活動期に向けて準備をする貯蔵の時期でもあります
イネ科の草は地上部を枯らせ、エネルギーを地下へと蓄えます
すべてのものが種に帰るこの時期こそ、成熟したものが"0"へと還りまた生まれる、命の巡りの神秘さを感じられる気がします(だから0は輪の形なのでしょうか...)
そして先日の新潟松の海岸林再生作業の合間、奇跡のような命の軌跡に遭遇することができました
今もなお伸び続ける阿賀野川河口の砂丘、その名のごとく"新たな潟"を作ろうとしています
日本海側では最大級の越後平野、海岸線には11もの砂丘列が海と並行するように並んでいます
この砂丘列形成は7000年前にもさかのぼります。
氷河期が終わり氷河が融け海水面が上昇、海水の内陸侵攻に伴い、土砂が押し寄せられ初期の砂丘列は形成されました。
その際内陸の河川が行き場を失い(運ばれた土砂が砂州を作りせき止めるので)"潟"となります
その後も何度か砂丘が形成され、それと共に潟も生まれてきました(福島潟、鳥屋野潟など)
今現在阿賀野川河口をせき止めるように海水は土砂を運び砂丘は伸び続けています
しかし、無機質な砂丘にどうして緑が生育できるのだろうか...
作業の合間足を延ばした阿賀野川河口に、大地と海とが織りなす、奇跡的な"命のゆりかご"づくりが見られました
|
|
|
|
海が運んできた土砂の上に、河川が運んできた流木 |
|
これが堆積し炭化
砂の大地の有機物となり草の生育を誘発しているのです
|
|
|
|
炭化した流木 土化し始めている砂 |
|
しかも、炭化した流木の上をさらに土砂が堆積することで、自然な起伏が出来上がり、土中の通気環境も維持されます
|
|
|
|
自然の様々な働きによってできた微地形 有機物を含んだ砂地に草が生え始めている |
|
草が生えればその後、砂地は一気に土化を加速、他の植物も生育できる環境へと徐々に地力をつけていきます
|
|
|
|
生えてきた草の根は細根が発達し、砂をつかんでいる、根には多種多様な菌根菌が共生しているため、砂地の生態系豊かになってくる |
|
力の無い全くの砂が、たくさんの命宿す土へと還る光景に、自然の奇跡、神秘さを感じずにはいられませんでした
大地の胎動感じる新潟、なぜここで松の海岸林再生をするのか、このお話をいただいた時よりもずっと強く思うのでした
自然がこんなにも生み出そうとしているのに、それをはるかに超えた速度の破壊力で人間が壊し続けているのだと...
もし、人間が自然の一員だとするならば、やはり役割や指名は命を繋ぐことかもしれないと思う
そしてそれは、これからを生きる世代にも感じてほしい
「地球の素晴らしさは生命の輝きにあると信じていた。地球はあらゆる命が織りなすネットで覆われている。
その地球の美しさを感ずるのも、探求するのも、守るのも、そして破壊するのも人間なのである」
翻訳者、上遠恵子さんの言葉です
上遠さんの翻訳されたレイチェル・カーソンの「センス・オブ・ワンダー」は水産生物学者であるレイチェルが破壊と荒廃へと突き進む私達へ向けた最後の遺言であり贈り物です
本には、上遠さんの訳を通してレイチェルとその甥ロジャーとの自然との触れ合いから感じる、美しいもの、未知なもの、神秘的なもの...たくさんの自然の奇跡が詰め込まれています
自然との共存という希望は、幼いものたちの感性の中にあるのかもしれない。
たとえ大人になったとしても、「センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目をみはる感性」は自然という力の源泉から遠ざかること、つまらない人工的なものに夢中になることなどに対する、かわらぬ解毒剤になるのです。
(センス・オブ・ワンダーより)
シュタイナー 千の葉学園の子供たちとの家づくり
まわりの自然の材料で作る、自分たちの場所
|
|
|
|
落ち葉が炭化し新たな命の土壌となる |
|
いつもの駆け回り締め固まった地面にみんなで炭をまきます...
積極的に自然と向き合い、関わることで自然の一員なのだと感じます
|
|
|
|
|
|
学園の子供たち、お客様のお子さんとの話はいつもハッと気づかされることばかりです
子供の見る世界は、大人が見ている世界よりもきっと大きくて、広くて、細かくて、深いそして何より敏感に、純粋にかんじているのだと...
幼いこどもたちがいつもワクワク、目を輝かせ続けられる、かけがえのない宝物がいつまでもあり続けますように...
破壊を続ける人間に対して、生み出そうとしている自然
決していつも優しいばかりではないけれど、大切なことを伝えようとしている
いつか出会う自分の子と、この自然の美しさ、不思議さ、厳しさ、未知なるものの神秘さ、共に胸ときめかせ、分かち合いたい...
投稿者 株式会社高田造園設計事務所